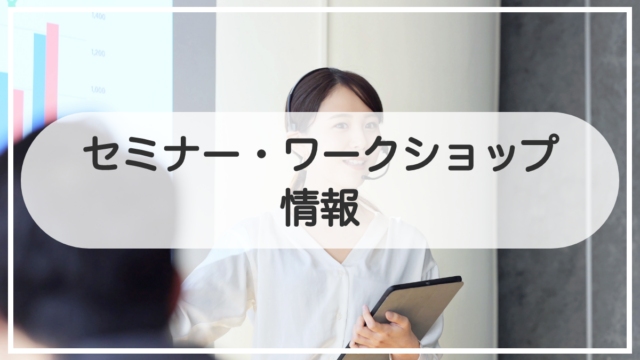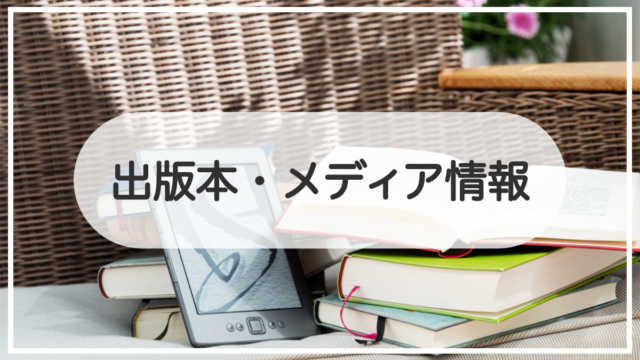ご相談事例集
がんばりすぎる人・恋愛で同じパターンをくり返す人へ
ここにご紹介するのは、実際のカウンセリングをベースにした「ご相談の一例」です。
プライバシー保護のため、内容には一部変更を加えていますが、ここに掲載することは承諾をいただいております。
- 頑張りすぎてしまう
- 恋愛で同じパターンをくり返してしまう
- LINEや相手の反応に振り回されてしんどい
- 人との距離の取り方がわからない
- 依存的な関係から抜けたいのに、離れられない
といった「よくあるお悩み」を、まとめました。
「これ、ちょっと自分に似ているかも…」
と感じるものがあれば、そこから読み進めてみてくださいね。
よくあるご相談テーマ
- 仕事も家事も頑張りすぎて、心が追いつかなくなる
- 好きになると尽くしすぎてしまい、最後は疲れ果ててしまう
- LINEの既読・未読に振り回されて、不安でいっぱいになる
- 相手に合わせすぎてしまい、本音が言えない・距離感がわからない
- 依存っぽい関係から抜けたいのに、つい元に戻ってしまう
- 「一人で生きていける自分」と「誰かにそばにいてほしい自分」の間で揺れる
ここからは、代表的な事例をいくつかご紹介します。
事例1|「全部私がやらなきゃ」と抱え込みすぎた40代女性
クライアント:40代女性(仮名:あかねさん)
/相談内容:
フルタイム勤務、家事もほぼワンオペ。
「仕事も家庭もちゃんとしなきゃ」「弱音を吐くのは甘え」と自分を叱咤しながら走り続けてきました。
ある日、些細なミスをきっかけに突然涙が止まらなくなり、
「もう限界かもしれないけど、休む勇気もない」
という状態でカウンセリングに来られました。
心理的背景
幼い頃から「しっかり者のお姉ちゃん」として期待され、
「頼るより、頼られる側」でいることが当たり前になっていました。
- 困っていても「大丈夫」と笑ってしまう
- つらくても「このくらいで弱音を吐くなんて」と自分を責める
そんな「がんばり癖」が、大人になっても続いていたケースです。
実施したアプローチ
- まずは「今、どれくらいしんどいのか」を言葉にしてもらい、“頑張りすぎている自分”を一緒に確認
- 「やらなきゃいけないこと」と「本当は手放してもいいこと」を仕分けするワーク
- イメージワークを使って、「ひたすら頑張ってきた自分」に寄り添い、責めるのではなく労うプロセスを重ねる
- 日常の中で「今日だけは人に頼ってみる」「5分だけ何もしない時間を取る」など、現実的な“ゆるめる行動”を提案
クライアントの変化
「やらなきゃ」が「やらなくてもいいこともある」に少しずつ変わり、
家族に「今日ちょっとしんどいから手伝ってほしい」と言えるようになりました。
「私ばっかり頑張ってる」から
「みんなで暮らしてるんだから、頼ってもいいよね」
という感覚にシフトし、
心身の不調も少しずつ落ち着いていきました。
事例2|「尽くしすぎて疲れる恋愛」から抜け出した30代女性
クライアント:30代女性(仮名:紗季さん)
/相談内容:
付き合うと、彼中心の生活になってしまう。
行きたい場所も合わせ、予定も合わせ、相手の都合を最優先。
「私ばっかり頑張ってる」
「彼の気分で、私の1日が決まる」
そんな恋愛パターンを何度も繰り返し、
「頭ではわかってるのに、同じことをしてしまう」と相談に来られました。
心理的背景
幼少期から「いい子でいると喜ばれる」経験が多く、
- 相手の期待を読む
- 気を遣って場を整える
ことが長所である一方、
「自分の気持ちを後回しにするクセ」が根深く残っていました。
「嫌われるくらいなら、我慢する方がマシ」という思い込みが、恋愛に強く出ていたケースです。
実施したアプローチ
- イメージワークで「彼に合わせているときの自分」の内側の声を丁寧に聴いていく
- 「合わせていない私は愛されない」という観念を見つけ、書き換えていく作業
- 日常では、「デートの行き先を一つだけ自分から提案する」「疲れている日は会わない選択をする」など、小さな自己主張から練習
- 「それをしているときの自分の気分」に意識を向けてもらい、“しんどくない関係とは?”を体感で探していく
クライアントの変化
「これが好き」「今日は少し疲れてる」と伝えられる回数が増え、
彼との関係も「一方的に尽くす」から「お互いに相談して決める」に変化。
「嫌われるのが怖くて、ずっと黙ってただけなんだなって気づきました」
事例3|LINEの既読・未読に振り回されて、仕事も手につかなくなっていた女性
クライアント:30代女性(仮名:美咲さん)
/相談内容
気になる人からのLINEが返ってこないと、頭の中がそのことでいっぱいになってしまう。
- 既読なのに返信がないと「何か気に障ること言った?」と自己否定
- 未読のままだと「嫌われたのかも」と不安で眠れない
- 返信が来るまでスマホを何度もチェックしてしまう
「こんなことで…と思いながらも、日常生活に支障が出ている」とのご相談でした。
心理的背景
過去の恋愛や家族関係で、
- 連絡が途切れる=見捨てられる
- 反応が冷たい=自分に価値がない
と感じる体験が積み重なっていました。
LINEは単なる連絡手段ですが、
美咲さんにとっては「自分の価値を測るモノサシ」になってしまっていたのです。
実施したアプローチ
- LINEの画面を見たときの身体感覚(胸のざわざわ・お腹の重さなど)を手がかりに、イメージワークで“過去の不安な記憶”に触れていく
- 「相手のタイミング」と「自分の価値」を切り離して考えられるよう、観念レベルの書き換えを実施
- 現実面では、
- 返信を待つ時間に「自分が落ち着ける行動リスト」を一緒に作成
- スマホチェックの回数を“段階的に減らす”練習を提案
- 「不安がゼロになること」を目標にするのではなく、「不安と付き合いながらも、自分の時間を戻していく」ことをゴールに設定
クライアントの変化
「返信が来ない=嫌われた」ではなく、
「今はたまたま向こうのタイミングじゃないだけかも」
という“別の解釈”を自分に渡せるようになりました。
スマホを見る回数も徐々に減り、
「気づいたら、仕事中に彼のことを考える時間が減っていました」と話されました。
事例4|人との距離感がわからず、「近づきすぎて疲れる/離れすぎて寂しい」をくり返していた女性
クライアント:30代後半女性(仮名:なおさん)
/相談内容
最初はすごく仲良くなるのに、
ある日突然「もう無理かも」と感じて距離を取ってしまう。
- 友だちや職場の同僚と、距離が近くなりすぎてしんどくなる
- でも、一人になると「嫌われたかな」「私が悪かったのかな」と落ち込む
- 「どれくらい近づいていいのか」「どこまで話していいのか」がよくわからない
というお悩みで来談されました。
心理的背景
幼少期に、家族の感情に振り回される経験が多く、
- 相手の気分を読む
- 相手に合わせて動く
ことが「安全でいる方法」になっていました。
そのため、“相手に合わせてベタッと近づく”か、“全部切って一人になる”かの極端なパターンになりやすく、
「心地よい中間地点」を知らないまま大人になっていたケースです。
実施したアプローチ
- カウンセリングの中で、「安心できる距離感ってどんな感じ?」を一緒に言葉にしていく
- イメージワークで、人との距離が近すぎる場面・遠すぎる場面を思い出し、それぞれの自分の感覚を丁寧に確認
- 「今、ちょっとしんどくなってきたかも」を早めにキャッチする練習
- 現実面では、「全部話す/何も話さない」の二択ではなく、
- 話題を選ぶ
- 会う頻度を調整する
など、“グラデーション”を使った付き合い方を一緒に設計
クライアントの変化
「ちょっとしんどいかも」と感じた時点で、
自分の中でブレーキをかけられるようになり、
「一気にゼロか100か、じゃなくていいんですね」
と話されました。
「この人とは月1で会うくらいがちょうどいい」など、
相手ごとに自分なりの距離感を持てるようになり、人間関係の疲れ方も変わっていきました。
事例5|別れた方がいいとわかっているのに、依存的な関係から離れられなかった女性
クライアント:40代女性(仮名:理子さん)
/相談内容
彼には他にも女性がいる。
約束も守らないし、連絡も気まぐれ。
頭では「このままでは幸せになれない」とわかっているのに、
別れを決断しようとすると激しい不安に襲われ、
結局関係をズルズル続けてしまう——というお悩みでした。
心理的背景
理子さんにとって彼は、
- 「一番ひどく傷つける存在」でありながら
- 「一番わかってくれる気がする存在」
という、矛盾したポジションになっていました。
その裏側には、幼少期の「不安定な愛情体験」があり、
「苦しいけれど、離れる方がもっと怖い」という感覚が根付いていました。
実施したアプローチ
- いきなり“別れる/別れない”の二択に行くのではなく、
まずは「この関係の中で、何が一番苦しいのか」をゆっくり整理 - イメージワークで、“彼にすがってしまう自分”と対話し、その奥にある寂しさや怖さにアクセス
- 「彼だけが私をわかってくれる」という観念を丁寧にほどき、
“自分自身との関係”を少しずつ育てていくプロセスを重視 - 現実面では、「いきなり完全に別れる」ではなく、
- 連絡頻度を減らす
- 会う場所・時間を自分主導で決める
など、コントロール感を少しずつ取り戻す段階を踏む
クライアントの変化
時間をかけて、「彼がいるから安心」ではなく、
「彼がいなくても、私は私で生きていけるかもしれない」
という感覚が育っていきました。
最終的に理子さんは、自分のタイミングで関係を手放す選択をされ、
「寂しさはあるけれど、あの頃のような“生きていけない不安”とは違います」と話されました。
事例6|一人は嫌いじゃない。でも、ふと将来が怖くなる40代独身女性
クライアント:40代女性(仮名:ゆかりさん)
/相談内容
一人の時間もそれなりに楽しく、仕事もやりがいがある。
友だちもいるし、大きなトラブルもない。
でも、夜ふとした瞬間に、
- 「このままずっと一人だったらどうしよう」
- 「親がいなくなったら、私は誰と生きていくんだろう」
と、言いようのない不安に襲われることが増えたとのことでした。
婚活もしてみたものの、「頑張らなきゃ感」が強くなり疲れてしまい、
「このままでいいのか」「何かしなきゃ」と焦りだけが募っていました。
心理的背景
ゆかりさんは現実的にも精神的にも自立していましたが、
その分、「誰かに甘える」「頼る」経験が少ないまま大人になっていました。
- 一人でいられる
- でも、本当は人恋しい
この二つの気持ちの間で揺れ続けて、
「どちらを選んでも間違いな気がする」という感覚に陥っていたケースです。
実施したアプローチ
- まずは「一人でいる私」「誰かといたい私」それぞれの本音を整理
- イメージワークで、“未来の自分”に会いに行き、
- どんな暮らしをしていると安心なのか
- どんな人間関係があれば心地よいのか
を具体的にイメージしてもらう
- 「結婚する/しない」「誰かと暮らす/一人で暮らす」といった二択ではなく、
もっとグラデーションのある“生き方の選択肢”を一緒に探る - 現実面でも、
- 仕事以外のつながりを少しずつ増やす
- 興味のあるコミュニティに一歩踏み出してみる
など、“安心できる関係の土台”を育てる行動を提案
クライアントの変化
「一人で頑張るか、結婚か、の二択じゃないんですね」
という気づきから、自分の選択肢が広がっていきました。
将来への不安がゼロになったわけではありませんが、
「今できること」と「今はしなくていいこと」の区別がつくようになり、
「焦りよりも、“今の自分の人生を育てていく”感覚が強くなってきました」
と話されていました。
最後に:もし、どこか一つでも心当たりがあったら
ここにご紹介したのは、あくまで「一部の例」にすぎません。
- 頑張りすぎてしまう
- 恋愛で同じパターンをくり返してしまう
- 距離感や依存がテーマになりやすい
そんな方のご相談を、これまで多くお受けしてきました。
「ちゃんとしなきゃ」と踏ん張ってきた分、
誰かに話すこと自体が、最初の一歩になることもあります。
「私の場合はどうだろう?」
「一度、話を聴いてもらいたいな」
と感じてくださったときは、どうぞ遠慮なくご相談くださいね。