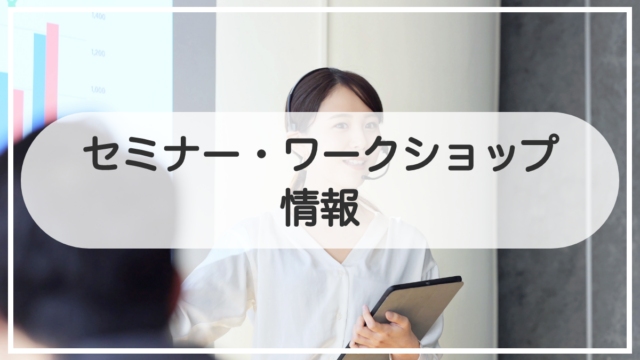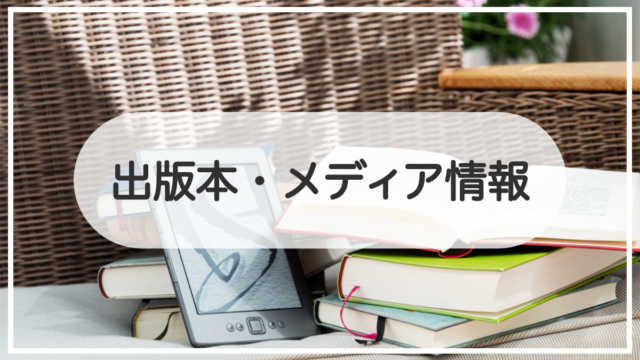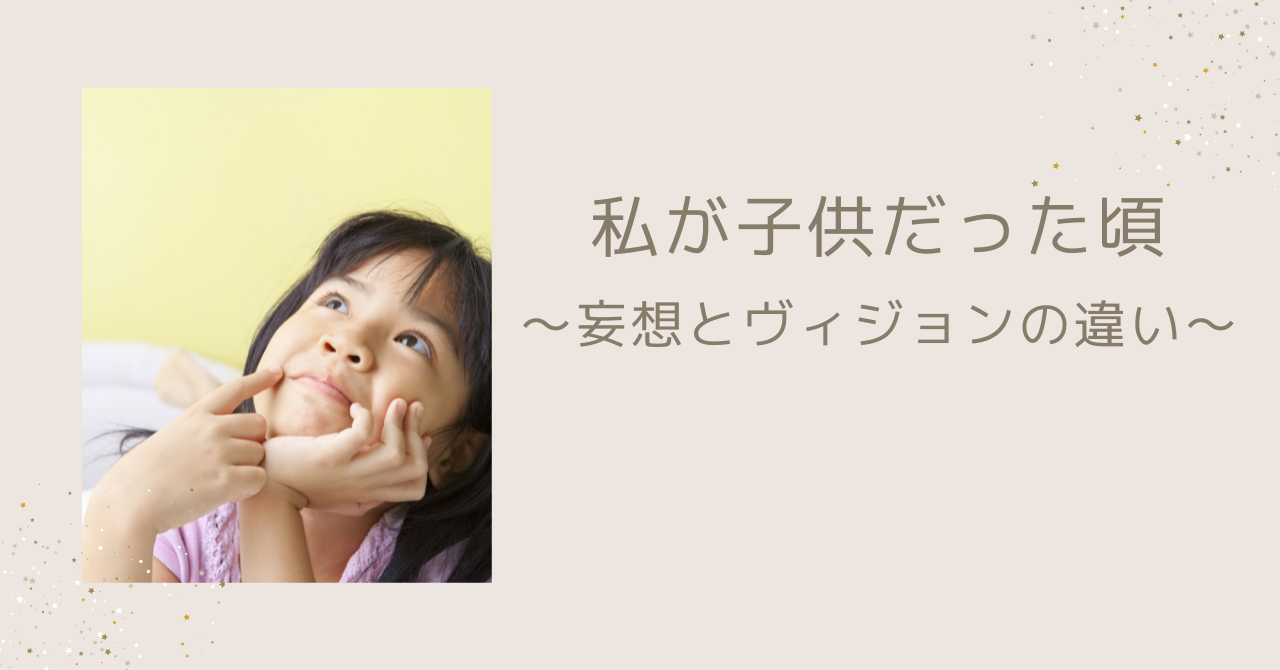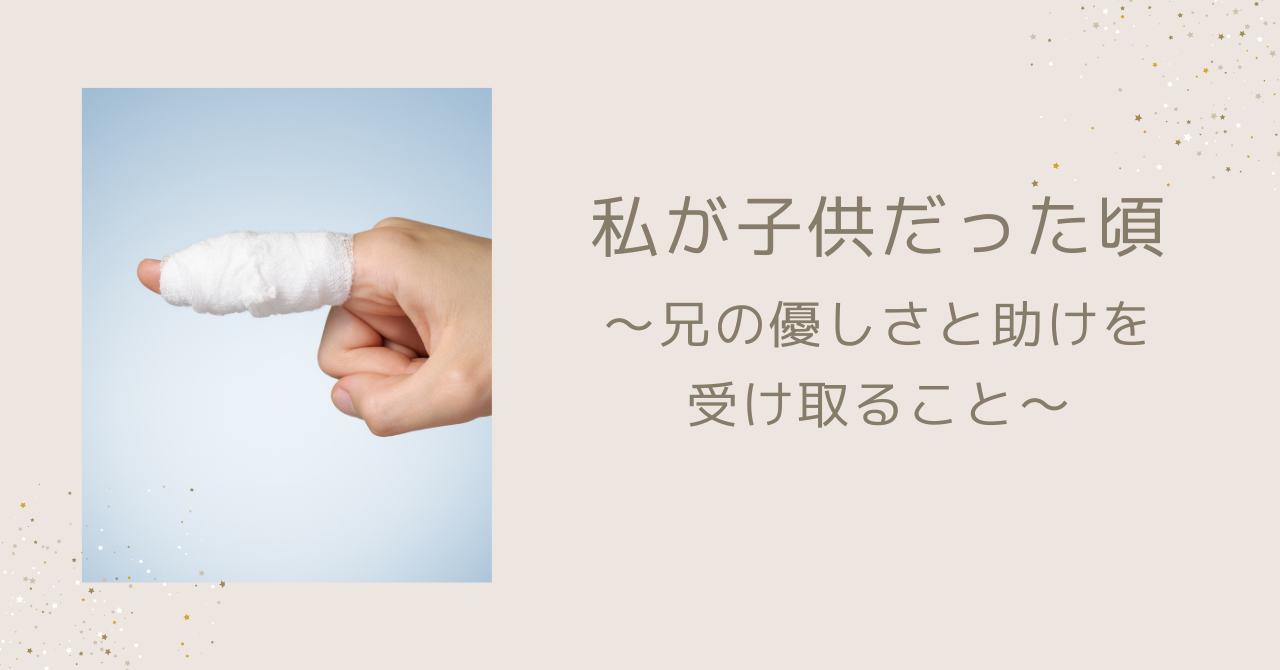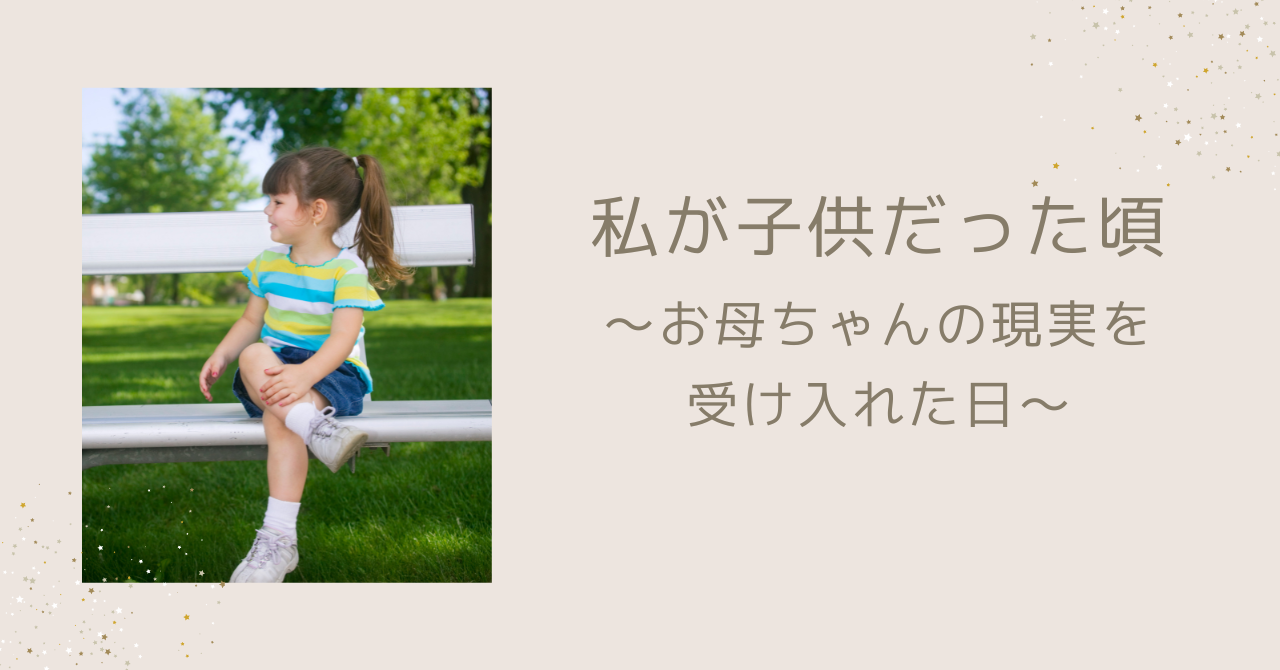幼少期の環境と女性性の欠如
私が小学校に入学するまでは、我が家は、父と母、兄と私という4人家族でした。 父は会社勤め、母は自宅で内職という状態でしたから、母は日中家には居るのですが、結構忙しく仕事をしていました。 ですので、兄にくっついて遊びに行くのが、私の日課でした。
いつも年上の男の子達と遊んでいるので、遊びも女の子らしいものから程遠く・・・
おまけに、髪の毛を切るのは、いつも母でしたから、兄と同じようにバッサリと刈られてしまい、髪形も女の子らしいとは言えず・・・
着る物も基本的には兄のお古ですから、スカートというものがなく、ピンク色なんて存在しません。
今思うと、私が女性性というものを伸ばすには、ちょっと難しい状態であったと思うのです。 母は男勝りで気が強く、おしゃれやメイクになんて、まるで興味がない人でしたから、余計だったかもしれません。
妄想の世界へ
そんな頃、私の妄想族の基本ができたのかもしれません。
そう!私は妄想族だったのです。 一応、注意事項として書いておきますが、暴走族ではなく、妄想族です。
普段、女の子らしいということからかけ離れて生活していましたが、だからと言って私が男の子な訳ではなく、当然ですが、女の子の部分も持ち合わせていた訳です。
『リカちゃん人形で遊びたいな』 『髪の毛を伸ばして、かわいい髪飾りなんかつけてみたいな』 『スカート、レースの付いたスカートをはいてみたいな』
そんな事を思っていましたが、父や母には言えませんでした。 言ったこともあったかと思うのですが、『うちには、お金がないから、我慢してな』そんなことを母に言われていました。
食べる物にも困るというような状態ではありませんでしたが、確かに贅沢ができるような経済状態ではなかったかと思います。 とはいえ、今思えば、中流、普通、平均的な家庭だったのではないかと思うのです。
とにもかくにも、うちが貧乏だと思い込んだ私は、親に何かを買ってくれとお願いできない子になっていました。 子供って、親を悲しませたくないんですよね。 親の助けになりたいと思っているんですよね。
そんな事は、今だから言えることで、当時は、『うちのお母ちゃんは、ケチだ』『うちのお母ちゃんは、優しくない』と思っていました。
ですから、私が女の子らしいことができないのは、全てお母ちゃんのせいだと思っていたようです。
妄想が膨らむ
よって、妄想が始まります。 『お母ちゃんが、綺麗で優しく、お金持ちだったら・・・』
当時、テレビドラマでよくやっていたような、お金持ちの奥様風をイメージしていました。
オホホホホッ・・・と、手を口に当てて笑い、お出かけの時は、つばの大きい帽子をかぶって、手袋なんかしちゃっているお母様を妄想する私。
自分の母親が、お母様だったら、娘の私はお嬢様。 お嬢様と言えば、長い髪をクルクルと巻いて、大きなリボンなんかを付けちゃって、ピラピラレースがついた、かわゆいワンピースなんかをお召しになっているわけで、おやつは、手作りのケーキで、お出かけは全て運転手つきの車。 (あくまでも、当時の私の妄想です・・・)
ムフフフフッ・・・と、膨らむ妄想。
妄想とヴィジョンの違い(心理学的視点)
もちろん、どれだけ妄想しても、母がお上品になることはないのですが、それでも当時の私は現実から目を背け、夢見ることで心のバランスを取っていたのです。
人間、自分の力ではどうにもできないと思うと、妄想に走ってしまうことがあるようです。
心理学では、このような状況を「心理的逃避」と呼びます。人は現実が苦しく、変えられないと感じると、空想や妄想の世界に逃げ込むことがあります。特に子供は、現実を変える手段が限られているため、想像の世界を通じて心の安定を保とうとします。
しかし、妄想とヴィジョンとは全然違います。
妄想は、あくまでも現実逃避の一環であり、そこに「実現可能性」は意識されていません。そのため、実際に行動を起こすこともなく、単なる夢想に終わります。
一方で、ヴィジョンは、「未来に対する具体的な目標やイメージ」であり、これが実現できると信じることで、人はそれに向かって行動を起こします。
心理学では、この違いを「学習性無力感」と「自己効力感」の差とも言えます。
- 学習性無力感:何をしても無駄だと学習してしまうと、人は行動を起こさなくなる(妄想に留まる)。
- 自己効力感:目標達成が可能だと信じることで、行動を起こす(ヴィジョンを現実化する)。
まとめ
妄想とヴィジョンの違いは、現実に変えようとする行動があるかどうか。
幼少期の私は、現実を変えられないと感じ、ただ妄想の世界に逃げ込んでいました。 しかし、心理学的に見ると、妄想に留まるのではなく、「この未来は実現可能だ」と信じることで、ヴィジョンに変えていくことが重要です。ただし、変えられないものをヴィジョンと捉えてしまうと、かえって無力感を強めることにもなります。本当に変えられることと、そうでないことを見極めることも大切なのです。
「私にはできる」という自己効力感を持つことで、妄想ではなく現実を変える力に変えていくことができるのかもしれません。
※「私が子供だった頃」シリーズとして、過去の記事に加筆修正を行い、新しい内容を追加しました。