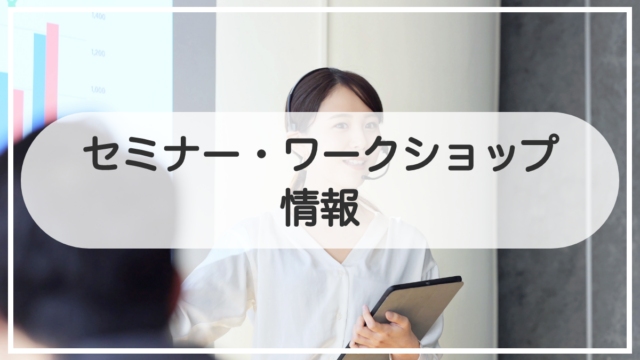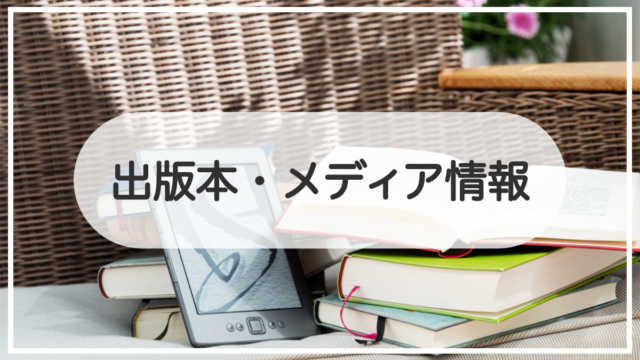出張で東京に行った大阪人が必ず直面するのが「エスカレーターどっち問題」。
大阪では右に立つのがマナー。ところが東京では左に立つのが当たり前。
エスカレーターに乗るとき、ちょっとした“社会の縮図”が顔を出すのをご存じですか?
大阪では右に立ち、東京では左に立ち、名古屋では右と左が入り乱れる。
たった数秒の出来事なのに、私たちは「自分の習慣を守るか」「周りに合わせるか」で迷ってしまう。
この小さな“あるある”には、人間の心理がぎゅっと詰まっています。
習慣のあるある:体が勝手に動く
大阪人が東京でエスカレーターに乗ると、気づけば右に吸い寄せられている。
まるで磁石に引き寄せられるかのように。
これは「筋肉メモリー(身体記憶)」の仕業。
習慣というのは、頭で考えなくてもできるように“無意識の領域”に刻まれていきます。
だから「ここは東京だから左」と理解していても、無意識のプログラムが「いや、右だ!」と主張してくる。
あるあるで言えばこんな感じです。
- 朝起きたら、無意識にスマホを手に取っている
- ダイエット中なのに、自動的にコンビニでお菓子コーナーに立っていた
- 「今日は麦茶にしよう」と思ったのに、気づけばコーヒーを淹れていた
人は「考えるより慣れ」を優先する生き物。だから、習慣に逆らう行動を取ろうとすると、必要以上にエネルギーを消耗してしまうのです。
同調のあるある:“人の目センサー”がピコピコ作動
習慣だけでなく、周りの目も私たちを動かします。
たとえば東京で右に立ったまま動かない自分。後ろからの冷たい視線を感じた瞬間、心の中で“人の目センサー”がピコピコ鳴り始める。
このセンサー、日常でも大活躍(?)しています。
- 飲み会で本当は帰りたいのに、みんなが2次会に行くからついて行ってしまう
- 本当は黒が好きなのに、みんながピンクを選んでいると「私もピンクで…」と言ってしまう
- 会議で「それ違うんじゃない?」と思いつつも、空気に飲まれて「はい、それで大丈夫です」と発言してしまう
心理学ではこれを「同調行動」と呼びます。
アッシュの同調実験でも、多くの人が“間違ってるとわかっていても周りに合わせる”という結果が出ました。
人の目を気にするのは、恥ずかしがり屋だからではなく、群れで生き延びてきた人間の本能なんです。
曖昧さのあるある:一番困るのは“どっちでもいい”
名古屋のエスカレーターは、右も左も人が混在している。
右に立てば「なんで右?」、左に立てば「なんで左?」と言われそうな気がして固まる……。
これ、恋愛でも仕事でも日常的に起きています。
- 「好きなの?好きじゃないの?」とハッキリしない関係にモヤモヤ
- 上司から「好きにやっていいよ」と言われて、逆に困る
- 友達に「なんでもいいよ、任せる」と言われたときに限ってお店が決まらない
心理学的に言えば、これは「曖昧さへの不耐性」。
人は自由を喜ぶはずなのに、自由すぎるとかえって不安になる。
ルールがあったほうが安心して動けるのは、実は自然なことなんです。
エスカレーター問題は人生の縮図
結局のところ、エスカレーターの立ち位置は「人生あるある」とつながっています。
- 東京で冷たい視線にビクビク → SNSで“いいね”の数を気にして発言を変える自分
- 名古屋で曖昧さに固まる → 「友達以上恋人未満」で身動きできない恋愛の自分
- 大阪で水を得た魚のように右に立つ → 気心知れた友達の前でだけ素を出せる自分
私たちはいつも、「周りに合わせるか」「自分を貫くか」の間でゆらゆら揺れているのです。
まとめ
- 習慣は“筋肉メモリー”として体に染みついている
- 人は“人の目センサー”に反応して同調行動をとる
- 曖昧さはかえって不安を生む
- エスカレーターの立ち位置は、日常のあらゆる場面の“あるある縮図”
次に出張でエスカレーターに乗るときは、ただ流されるのではなく「いま私の心理は習慣?同調?曖昧さストレス?」と観察してみてください。
ちょっとした心理実験になるかもしれません。
▼あわせて読みたい関連記事
▼関連note記事
今回の記事は、noteで連載中のエッセイシリーズ
『“私だけ?”って思ってたけど、みんなそうだった。』#14「エスカレーターの立ち位置迷子と、推しの隠蔽」ともつながっています。
日常をユーモアたっぷりに切り取ったnote版も、ぜひあわせてお読みください。