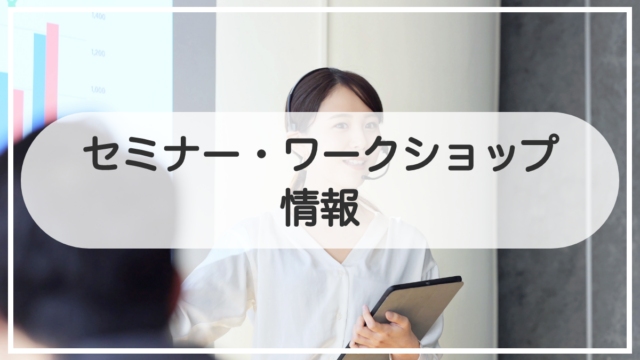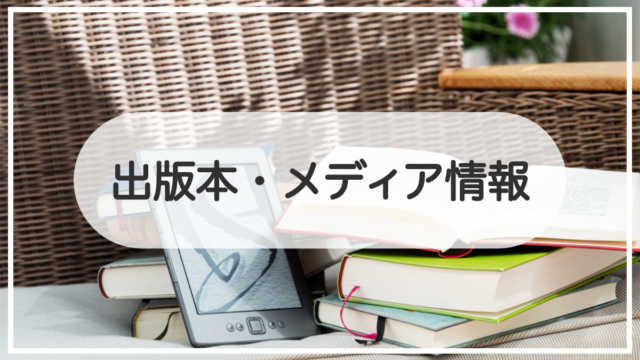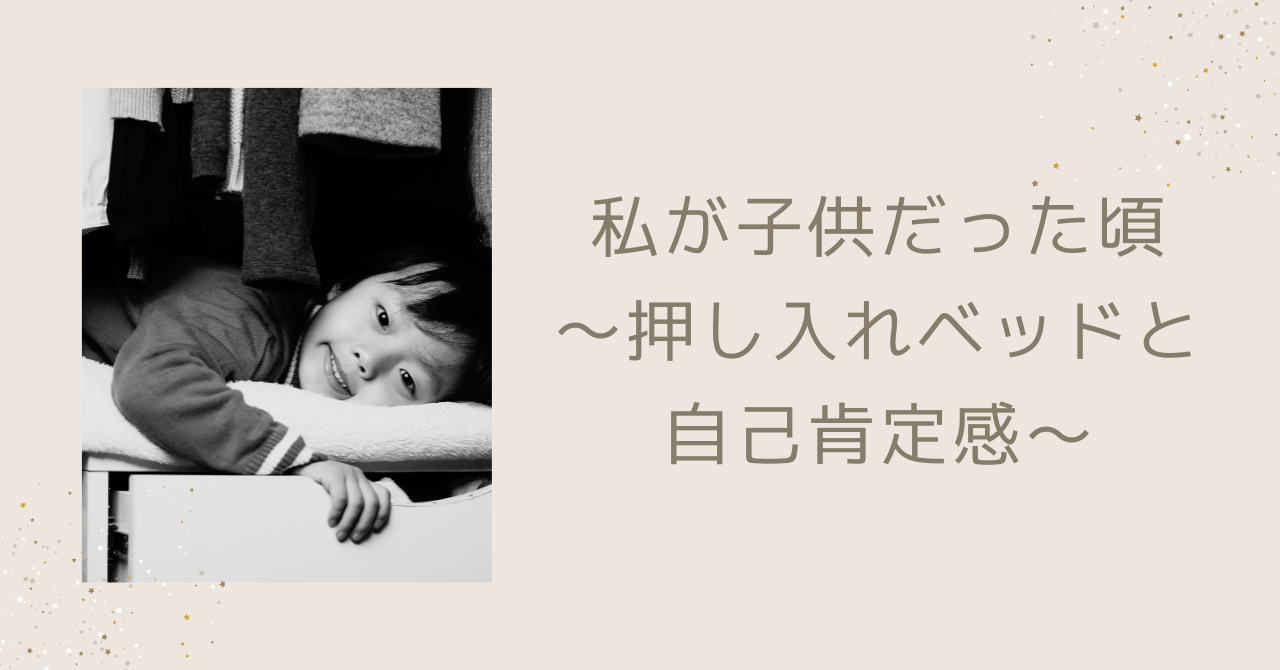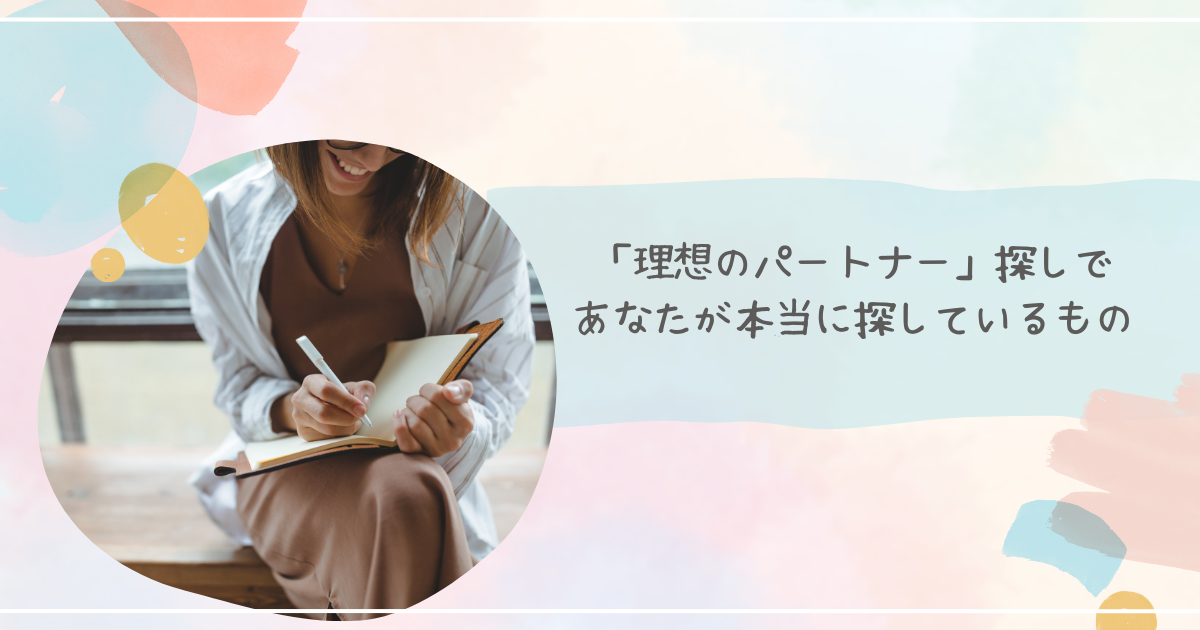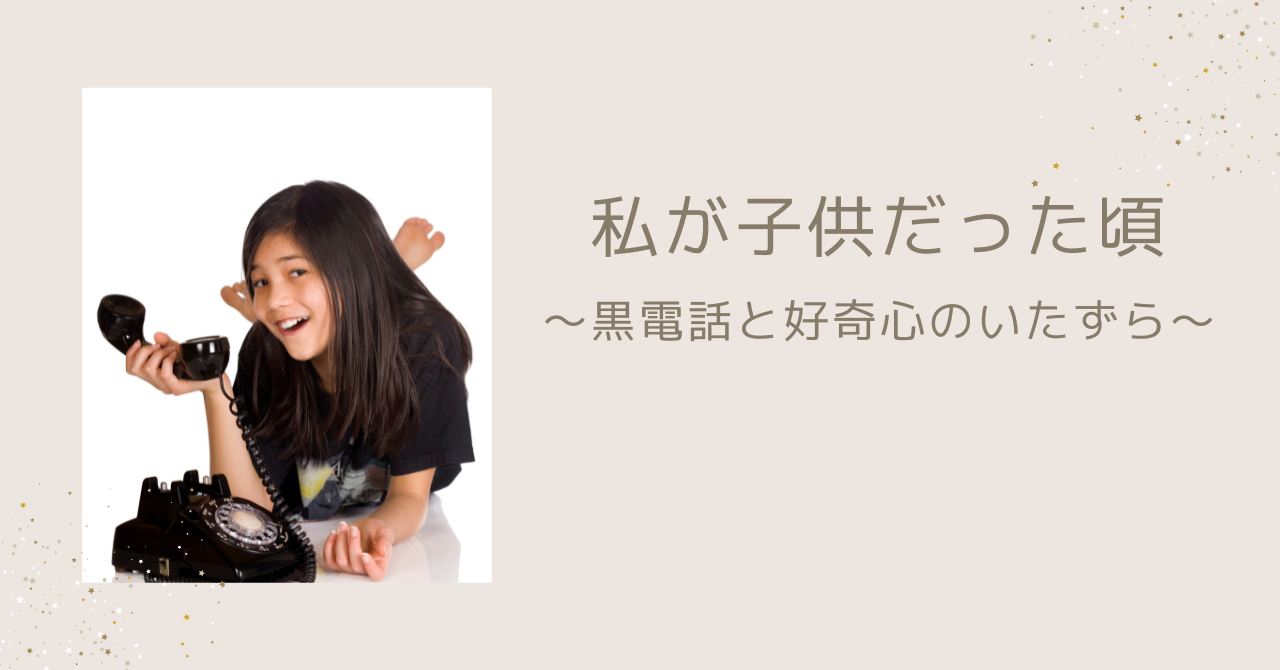わたし、昔、『ドラえもん』でした。
と言っても、全身真っ青だったわけではなく、お腹にポケットがついていたわけでもありません。
実は、私が幼い時のベッドが、押し入れだったのです。
押し入れがベッドになった理由
ドラえもんは、のび太くんの家に居候していますが、のび太くんの部屋の押し入れで寝ています。
あれと同じように、何歳かはわかりませんが、小学校に入るまでは、押し入れが私のベッドで、押し入れの下段が私、上段が兄となっておりました。
なぜそうなったかは知りませんが、おそらく少々狭い家に住んでいたから、父と母、私と兄のお布団を敷くと、部屋が手狭になるためではないかと思います。
別に押し入れに押し込められていたわけではなく、寝るときは押し入れの扉はオープンにされ、すぐ横で父と母が寝ていたように思います。
幼少期の読書体験と自己肯定感
そんな押し入れ生活のなか、特に思い出深いのは、兄に絵本を読んであげていたこと。
おそらく私は4歳か5歳だったと思います。 と言うことは、兄は6歳か7歳。 それなのに、兄が寝る前に、私が兄に『赤鬼さん』の絵本を読んであげていたのです。
ああ!なんと利発な子供だったのでしょう!!
小学校入学前に、ひらがなは全て読めていたのです。 昔から本は好きでしたね。
この頃、よく母に『昌代はかしこいな~』とか『昌代は本を読むのが上手やな~』と言われていたような記憶があります。
ここで心理学的なポイント!
自己肯定感は、幼少期に親や周囲からどのようなフィードバックを受けるかによって大きく影響を受けます。
特に、褒められることで「自分には価値がある」と感じることができるのです。
褒められることがもたらす影響
子供は、親から褒められると嬉しいもの。
人間、褒められれば幸せです。 もちろん子供ですから、親から褒められるというのは、最高のご褒美になります。
この経験からもわかるように、子供のやる気を引き出すには、「できたことを褒める」ことが大切なのかもしれません。
心理学では、これを「自己肯定感の形成」に関連すると考えます。
「自分が認められた」「役に立てた」という経験が積み重なることで、自己肯定感が育まれるのです。
それでも苦手なものはある ~成功体験の偏り~
そんな記憶があるなか、今日も数学の苦手さを自覚しながら生きています。
母に褒められたのは読書に関することだけで、算数についてはほとんど褒められた記憶がありません。
でも、一つ自信が持てるものがあれば、それが心の支えになり、自分を肯定できるようになるのだと思います。
ここで再び心理学的なポイント!
人は、幼少期に「得意だ」と認識したものには自信を持ちやすく、反対に「苦手だ」と刷り込まれたものには、やる気を失いやすいのです。 これを「自己効力感(Self-efficacy)」と言います。
つまり、「読書が得意で褒められた経験」は成功体験として積み重なり、自己効力感を高めた。
でも、算数に関しては成功体験が少なかったため、「自分は算数が苦手」と思い込むようになったのです。
「算数が苦手でも、本が読めればいいじゃないか!」と、自分に言い聞かせながら今日も生きているわけですね(笑)
【まとめ】
幼少期の経験は、自己肯定感の土台を作る大切な要素です。
親や周囲の大人から「できたこと」を認められると、自分に価値があると感じやすくなります。
反対に、苦手なことばかり指摘されると、「自分はダメなんだ」と思い込みやすくなります。
特に、幼少期の成功体験は、その後の自信に大きく影響を与えます。自己効力感(Self-efficacy)が高いと、苦手なことに対しても「努力すればできるかもしれない」と考えられますが、低いと最初から諦めてしまうことが多くなります。
たとえ算数が苦手でも、一つでも「これは得意だ」「自分にはこれがある」と思えるものがあれば、それが自己肯定感の支えになります。
できないことばかりに目を向けるのではなく、「できること」「好きなこと」を大切にしていくことが、自分を肯定する力につながるのです。
※「私が子供だった頃」シリーズとして、過去の記事に加筆修正を行い、新しい内容を追加しました。