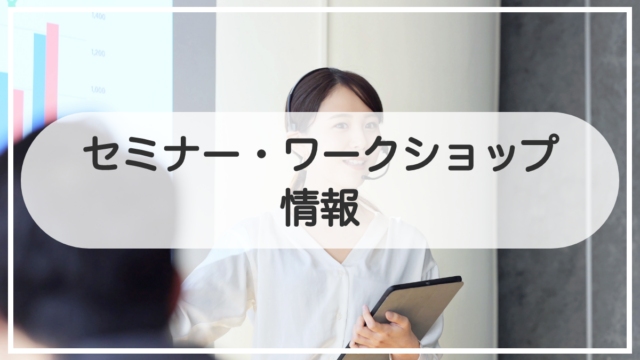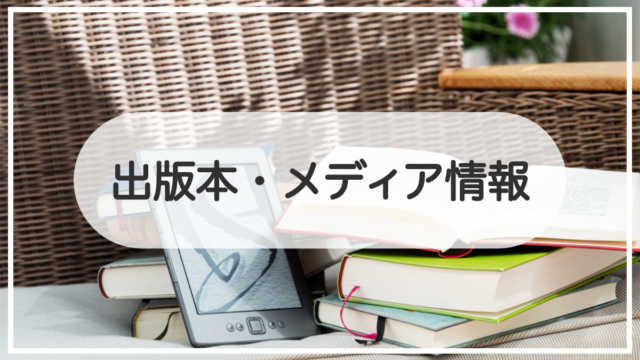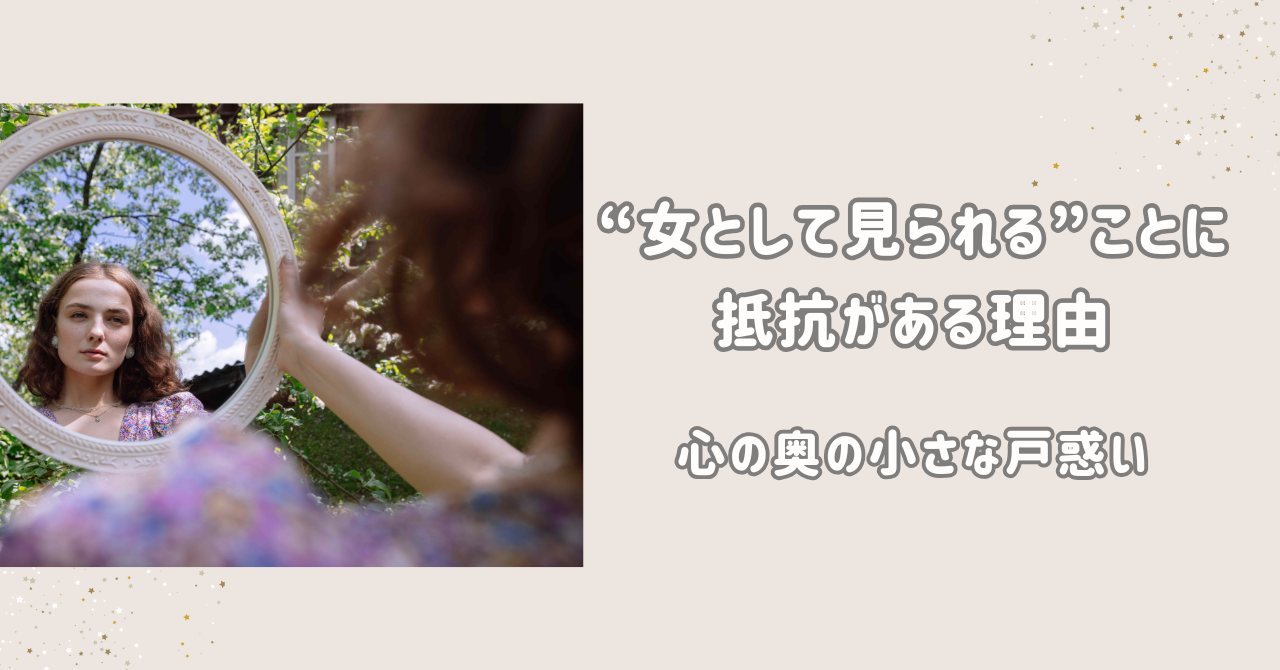「自立してるね」「頼りになるよね」——たぶん、よく言われてきた言葉。
でも、夜ふとひと息ついたとき、ふわっと湧いてくる、言葉にしづらい不安。
部屋は静かで、やることはちゃんと終わってる。
だけど、なんだか落ち着かない。
「何が足りないんだろう?」と、頭の中だけが忙しくなっていく。
仕事も人間関係もそつなくこなして、「自立しててすごいよね」と言われるけど、
ふと夜にひとりになったとき、「安心できる場所ってどこにあるんだろう?」と思ったことがある人へ。
この記事では、「がんばれるけど、安心できない」——
そんな“自立した私”の奥にある、ちいさな戸惑いや寂しさを、
ちょっと笑いながら、ひもといてみたいと思います。
“大丈夫なふり”が、だんだん板についてきた
「大丈夫?」って聞かれたとき、反射的に「うん、大丈夫!」と返してしまう。
実際は、そこそこしんどい。寝不足だし、心配ごともある。
でも、なんか「大丈夫です」って言ったほうが早い気がして、
気がつけば、それが“いつもの私”になっていた。
最初は、“がんばらなきゃ”って思ってた。
でもそのうち、“がんばれる自分でいるほうが楽”になってくる。
弱音を吐いて心配されるより、「さすが!」って言われる方が気がラクで、
気づけば「頼れるポジション」にすっかり定着していた。
でも、こういう“安心させる側”にいると、
ふとした瞬間に「私、誰にも甘えてないな……」って気づくことがある。
それは、ちょっと切ない発見。
ほんとは、誰かに「よくがんばったね」と言ってほしいし、
「なんか元気なさそう」と察してくれる人がいたら、泣けてくるかもしれない。
だけど、それを言えない・見せられない自分がいる。
心理学で言えば、これは「適応戦略」のひとつ。
環境にうまく対応するために、自分の感情を抑えて“ちゃんとした人”を演じる習慣。
そのクセが長年かかって定着すると、
“本音”のほうが、どこかに行方不明になることがあります。
だから、「ちゃんとしてるね」って言われても、
どこかむなしかったりするんですよね。
“安心”がどこにあるのかわからない
ひとりでも大丈夫。
やろうと思えばなんでもできる。
困ったことがあっても、誰かを頼るより、ググったほうが早い——そんな自立フル装備でここまで来た。
でもあるとき、ふと思うのです。
「で、私はいつ安心するんだろう?」
ひとりでがんばることに慣れてしまうと、「助けてもらえる」「甘えても大丈夫」という感覚が、少しずつ遠ざかっていくものです。
頭では「ちゃんとできてるし、平気」と思っていても、心のどこかではこうつぶやいているかもしれません。
「安心って、どうやって得るんだっけ……?」
それは、家の鍵をかけたはずなのに何度も確認してしまうような感覚。
自分で自分を守る術は身についたけど、誰かに守られることや、ただ一緒にいることで安心できる感覚は、いつの間にか置いてきてしまったのかもしれません。
この「安心がどこにあるのかわからない」感じには、ちょっとした心理的な背景があります。
たとえば、子どもの頃に「ちゃんとしていれば安心が得られる」と学習してきた人は、「役に立つこと=存在価値」と思いやすくなります。
でも実際のところ、人との関係って“役に立つかどうか”よりも、“一緒にいてホッとするか”のほうが大事だったりするんですよね。
なのに、「安心したい」って思ったときに、自分の中から出てくるのは
「もっとちゃんとしなきゃ」だったりする。
だから、ずっとがんばってしまう。
そのうち、「自分のための安心」よりも「周りを安心させること」のほうにエネルギーを使ってしまうようになる。
そうすると、本当に休みたいときに、自分の居場所がわからなくなるんです。
「ひとりで平気」と「ひとりが平気」はちがう
「ひとりでも大丈夫」
「むしろ、ひとりの時間がないと無理」
そう思ってきたし、実際それでうまくやってきた——ように見える。
でも、ある夜ふと、静かすぎる部屋の中で感じるこの違和感。
なんだろう、この「ひとりで平気です!」の裏側にある、ちょっとした空洞みたいなもの。
「ひとりで平気」という言葉、よく考えてみるとちょっと不思議なんですよね。
それって、強さの表明なのか、それとも寂しさのカモフラージュなのか。
実はこのふたつ、「ひとりでいられること」と「ひとりが好きなこと」は、まったく別物だったりします。
「ひとりでいられる」は、生きる術。
でも「ひとりが好き」は、心が満たされた状態でこそ言えるもの。
心理学的に言えば、これは自己充足と防衛的回避のちがいみたいなものです。
たとえば——
・予定のない週末、誰とも会わずにNetflixとお菓子で過ごすのが幸せ!
→ 自己充足。心が満たされてる証拠。
・予定のない週末、誰にも連絡しない。誘われたら面倒だから“既読スルー”。
→ 防衛的回避。ちょっと心が疲れてるかも。
もちろん、どちらが悪いわけじゃないけれど、もし後者が続くなら、そこには「ひとりじゃないことが怖い」という感情が隠れているかもしれません。
本当は誰かといて安心したい。
でも、自分の内側にある不安や弱さが見えてしまいそうで、それがこわくて距離を取ってしまう。
だから、「ひとりがいい」って言葉で、そっとフタをしてきたのかもしれません。
そのフタを少しだけ開けてみたら、「ほんとは誰かにそばにいてほしい」っていう、ちょっと恥ずかしいけど、すごく自然な気持ちが顔を出してくるかもしれません。
“しっかり者”って、本当はちょっと不便
「しっかりしてるよね」
「頼りにしてる」
「○○さんがいてくれて助かる」
——そう言われると、なんだかうれしい。
でも、うれしいはずなのに、心の奥で「……またか」とため息が出る。
“しっかり者”って、便利なんですよね。
他人にとって。
ちょっとしたトラブルも「私がやるよ」と対応して、
気まずい空気も「まあまあ」と和ませて、
誰かが不安そうなときは「大丈夫、私がなんとかするから」と笑ってみせる。
——で、結局、自分の不安を誰にも見せられないまま、1日が終わる。
こうして“安心させる側”の役割が板についてしまうと、
「自分も安心したい」なんて感情は、いつのまにか居場所を失ってしまいます。
でも、本当は。
しっかりしてる人ほど、誰よりも「ちゃんと甘えたい」気持ちを抱えていたりするんです。
誰にも言えないだけで。
心理学では、こうした傾向を「役割の固定」と呼んだりします。
つまり、自分がいつも同じ“役割”を引き受けることで、他者との関係性を保っている状態。
その役割に自分を合わせていくうちに、
「しっかりした私」じゃないと、価値がないように思えてくる。
そしてやっかいなのは、この“しっかりキャラ”は他人が期待してくるだけじゃなく、
自分自身も気づかぬうちに、「これが私の役目」と信じてしまっているところなんです。
でも、本来“しっかり者”でいることと、“弱さを見せること”は両立できるはず。
むしろ、時には安心して崩れてもいい場所があるからこそ、
また笑顔で立てるのかもしれません。
——そう言いつつ、「そんな場所どこに?」と即答してしまいそうな人のために、
この記事のラストには、ちょっとしたヒントを残しておきますね。
「支えられること」に、なぜかソワソワしてしまう
「ちゃんとしてるね」と言われてきた人ほど、
人に頼られることには慣れていても、
頼られる側から外れた瞬間、なんとも言えないソワソワがやってくることがあります。
たとえば、落ち込んでいるときに誰かが差し出してくれた温かい言葉や、
仕事でちょっと助けてもらったときの「任せて大丈夫だよ」という一言。
頭では「ありがたい」と思っているのに、
心のどこかがザワつく。「いやいや、私がちゃんとやらなきゃでしょ?」と。
このソワソワの正体は、“役割の逆転”に対する違和感かもしれません。
自立してきた人ほど、支える側にまわることに慣れています。
だからこそ、いざ自分が「支えられる側」になると、
それはまるで、舞台の上でいきなり台本を取り上げられたような気分。
「次のセリフ、こっちじゃなかったの⁉」みたいな動揺がやってくる。
でも、ここでちょっと視点を変えてみると——
「支える・支えられる」は、固定された役割じゃないんですよね。
その瞬間その瞬間で、役割はゆるやかに入れ替わる。
たとえば、自転車を二人乗りしているとき、
ペダルを漕ぐのは片方でも、もう一人がしっかりとしがみついていてくれるからバランスが取れる。
(※本当は二人乗りしちゃいけませんけどね。昭和の恋愛ドラマあるあるということで…😅)
支えているのか、支えられているのか——その境目って、意外と曖昧です。
だから、「支えられてる私、ちょっと居心地悪い…」と思ったら、
まずはこう思ってみる。
「そっか、今は受け取るターンなんだな」って。
人生のバトンは、受け取る側も走っているんです。
たまには立ち止まって、バトンをもらうことも、ちゃんとレースの一部なんですよ。
「誰かに頼ってもいいのかも」と思える瞬間が増えてきたら
長いあいだ、“ひとりで頑張るモード”で生きてきた人にとって、
誰かに頼るとか、甘えるとか、そんなのはファンタジーの世界の話でした。
「自分が何とかしなきゃ」「弱さを見せたら終わり」——
そう信じて、たくさんのことを抱えて、乗り越えてきたからこそ今がある。
でも、不思議なもので、ある日ふっとこんな感覚が湧いてくることがあります。
「……もしかして、今の私は、ひとりじゃなくても大丈夫かもしれない」
もちろん、いきなり誰かにべったり甘えられるわけではないけれど、
たとえば——
・「大丈夫?」のひと言に、ちょっとホッとした
・お店で荷物を持ってもらったとき、素直に「ありがとうございます」が言えた
・「手伝おうか?」に対して、条件反射で断らずに、「うん、お願い」と言えた
ほんの小さな“委ねること”ができたことに気づいたとき、
それはもう、かなりすごい変化だったりします。
心理学的に言えば、「安心の感覚」が少しずつ回復してきた証です。
人に頼るのが苦手な人の多くは、過去に“信頼して裏切られた”経験や、
“助けを求めても届かなかった”記憶を持っていたりします。
だからこそ、ちょっとの安心、ちょっとの信頼が、自分の中に芽生えることは、
ものすごく尊くて、ものすごく価値がある。
まるで、硬く凍っていた地面に、やっと小さな芽が出てきたような、そんな瞬間です。
安心提供係、そろそろシフト交代しませんか?
「この場は、私がなんとかしないと」
「大丈夫?って聞く側でいないと」
気がつけば、そんな“安心提供係”の制服を着て今日も出勤している自分がいる。
制服の胸元には、ちゃんと「頼れる人」って名札付き。しかも自作。
でも、その名札——ちょっと重くなってきていませんか?
長く続ければ続けるほど、「弱音を吐く=役割放棄」のような気がして、
ますます自分の不安や疲れを隠すようになってしまう。
安心を与えるのは素晴らしいこと。
だけど、ときには自分が“受け取る側”になってもいいんです。
「私は大丈夫」って、誰に言ってたんだろう
「大丈夫」って、便利な言葉です。
聞かれたときに「うん、大丈夫」と答えるだけで、話が終わる。
助けようとした相手も、なんとなく安心するし、自分も少しホッとする。
でもこの「大丈夫」——
誰かに向けて言ってるつもりが、実は一番聞かせたかったのは、自分自身だったりするんですよね。
たとえば、疲れ果てて帰ってきた夜。
玄関のドアを閉めた瞬間に、靴を脱ぐのも面倒になるほど、エネルギー切れ。
でも、「ちゃんとしなきゃ」と思って、無理やり洗濯機を回して、明日の準備まで済ませる。
寝る前にスマホを見ながら、「私って、まぁまぁえらいよね」と自画自賛モードに突入する。
……これ、もう立派な「セルフ励まし」です(笑)
でも、その裏では、
「ほんとはちょっと休みたかった」
「誰かに頼ってみたかった」
そんな気持ちが、小さくうずくまっていたりする。
「大丈夫」は、優しさの仮面をかぶった“孤独の合言葉”になってしまうこともあるんです。
もちろん、「大丈夫じゃない」なんて簡単に言えない時もあります。
頼るって、ちょっと怖い。
弱音を見せると、相手に引かれるかもしれない。
そんな不安があるからこそ、「大丈夫」は鉄壁のガードになってしまう。
でも、いつも「私は大丈夫」と言い続けていると、
まるで“自立の呪文”を唱えているように、だんだんと本当の気持ちが遠くなっていくんですよね。
それって、少し切ないことかもしれません。
だからこそ、
「本当はちょっとツラいかも」
「実は助けてほしかった」
そんな気持ちを、ほんの少しずつでも“言葉にしても大丈夫”と思えるようになること。
それが、心の安心を取り戻していくカギになるのかもしれません。
“頼られポジション”から抜け出すには?
気づけば、周りから「しっかり者」「なんでもできる人」認定されている——そんなこと、ありませんか?
もちろんそれは、あなたの実力と努力のたまもの。
でも一方で、「あれ?なんで私ばっかり頼られてるんだっけ?」とふと疲れを感じる瞬間もあったのではないでしょうか。
頼られるって、最初は嬉しいんです。
信頼されてるってことだし、「期待されてる私」に、ちょっと背筋が伸びる。
でもそれが続くと、「私がなんとかしなきゃ」が当たり前になって、
いつの間にか“頼る”側の席が、空いてることにすら気づかなくなってしまう。
「私がやった方が早い」
「どうせ私が動くしかない」
そうやって、自分で自分を“便利な人”に仕立ててしまっていたりもします。
しかもやっかいなのは、「頼っていいよ」って言われたときに、どこかソワソワしてしまうあの感覚。
「えっ、そんなこと頼んでいいの?」
「甘えすぎって思われない?」
……って、脳内で勝手に審議会が開かれるパターン(笑)
でも実は、この「頼られポジション」に居続けることで、
自分の中にある“弱さ”や“人にゆだねたい気持ち”に、蓋をしてしまっていることがあるんです。
じゃあどうやって抜け出せばいいのか。
それは、ほんの小さなことから“ゆだねる”練習をすること。
たとえば——
・「これやってもらえる?」と、言葉にしてお願いしてみる
・「あ、それ助かった〜!」と、受け取ってみる
・「私も今ちょっとしんどい」と、タイミングを見て伝えてみる
“全部自分でやらなくていい”と体感すると、ちょっとした心の余白ができるんですよね。
その余白は、次に誰かのやさしさが入ってくるスペースになります。
そして大事なのは、誰かに頼ったからといって、あなたの価値が下がるわけじゃないということ。
むしろ——
「この人、がんばってきたんだな」
「ちゃんと頼ることもできるんだな」
そんなふうに感じてもらえることだってあるんです。
完璧な自立じゃなくていい。
ときどき肩を預けながら、ほどよく頼られ、ほどよく頼れる。
そんな関係性が、思っているよりずっと心地いいかもしれません。
“安心”って、どこから来るんだろう?
自立している人ほど、「安心」を外に求めにくくなることがあります。
「誰かに頼る」ことは、ちょっと不安。
「助けて」と言ったら、面倒な人だと思われるかも。
「弱さを見せたら、評価が下がるんじゃないか」——そんな思いが、ふとよぎってしまう。
だからこそ、なるべく自分でなんとかする。
「私、大丈夫ですから!」の笑顔を常にスタンバイして、今日も抜かりなくがんばってる。
でも実は、「安心」って、がんばりの先にあるんじゃなくて、
「今の自分でOK」と思える瞬間に、ぽっと芽生えるものなのかもしれません。
たとえば、家に帰って靴を脱いだときの、ふわっと力が抜ける感じ。
お風呂で「あ〜〜っ」と声が漏れちゃう瞬間。
誰かに「それ、わかるよ」って言ってもらえたときの、目に見えないホッと感。
あれって、特別な何かが起きたわけじゃないけれど、
「ここにいていい」って、自分に許可が出せたときに感じる“安心”なんですよね。
でも、自立を極めてきた人にとっては、
この「安心していい」がいちばん難しい。
だって今までずっと、「がんばる私」でなんとかしてきたから。
「安心しちゃダメ」っていうより、
「安心してもいいって、どうやってわかればいいの?」という感覚が、正直なところかもしれません。
だからこそ、はじめは「不安でも、安心してみようとする」くらいがちょうどいい。
安心は、完全に不安がなくなったときに訪れるものじゃなくて、
不安の中でも、少しずつ自分にOKを出しながら育てていくもの。
まるで、猫を信頼させるみたいに。
(急に抱っこしようとせず、まずはそっと隣に座って、じっと待つやつです)
安心は、あなたの中にもうすでに芽を出しているのかもしれません。
ただその芽が、「今ここは大丈夫」と感じられる場所を探しているだけ。
誰かと比べなくていい。
「完璧な私」じゃなくて、「ありのままの私」がちゃんと居場所を持てること。
そんな感覚に出会えたとき、
「もう、がんばり続けなくてもいいかも」って、ふと肩の力が抜けるかもしれません。
関連記事もどうぞ 📚
自立や安心感に関する理解を深めたい方は、以下の記事もご覧ください: