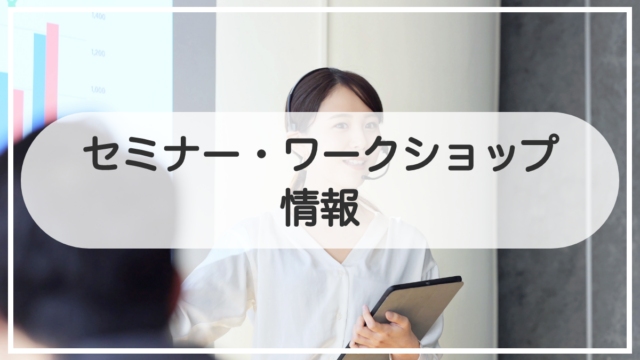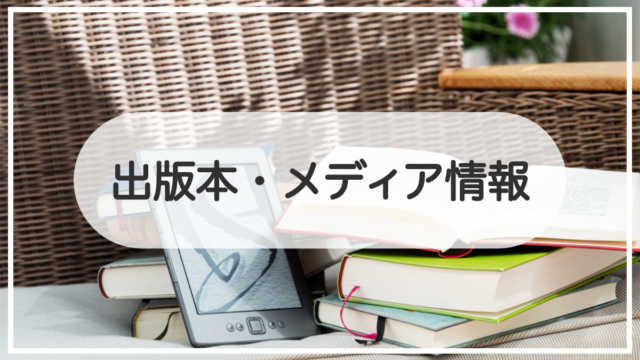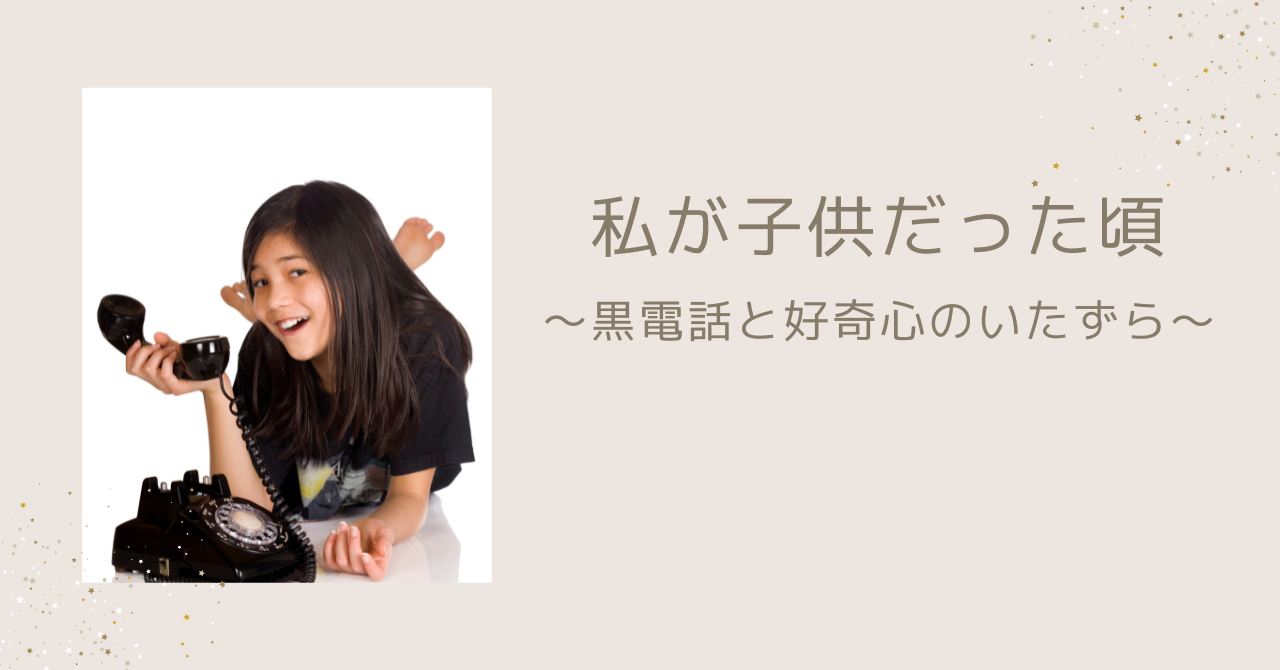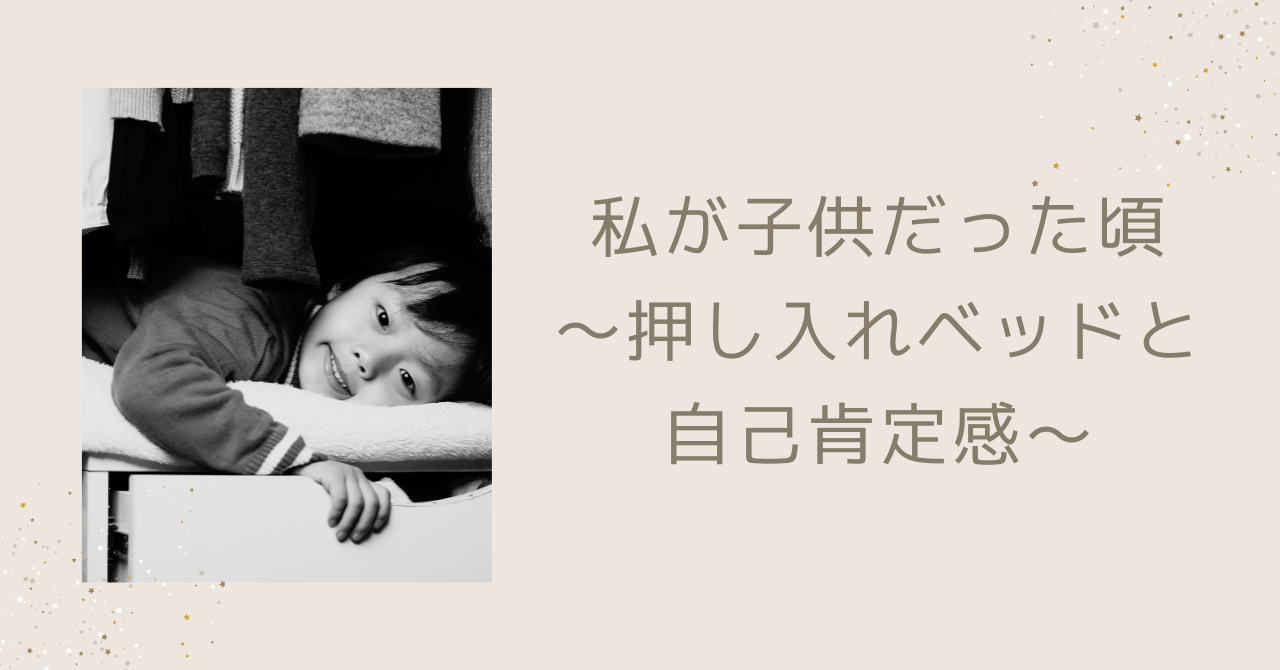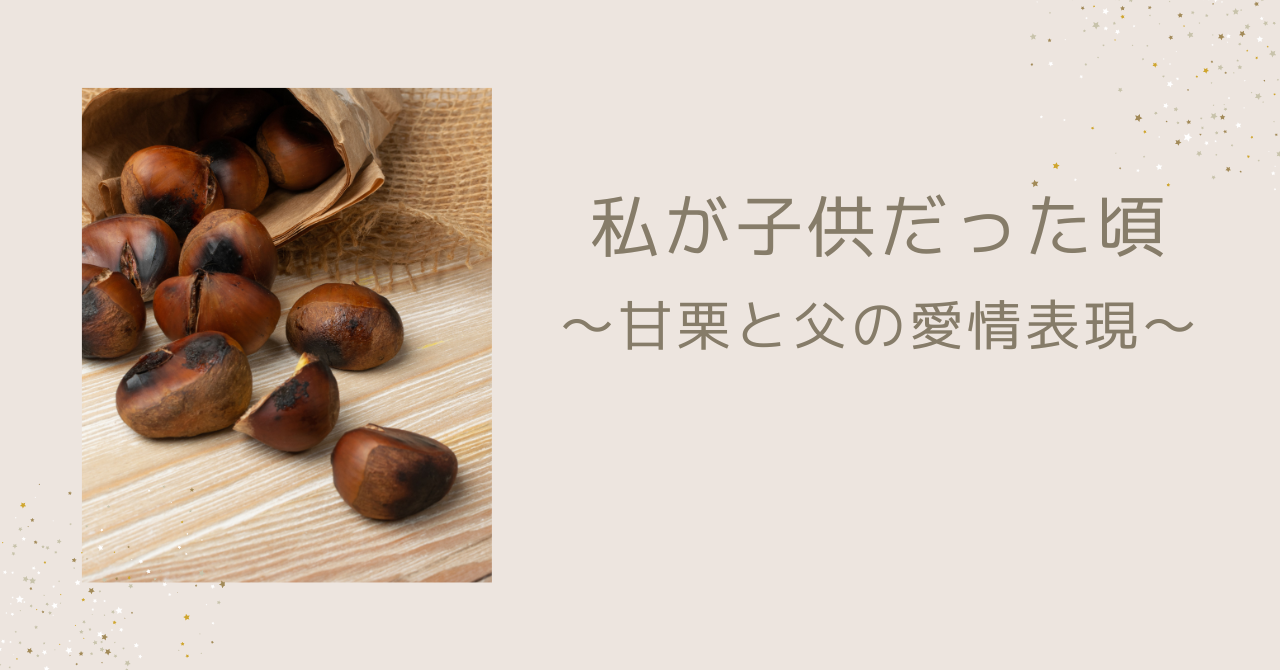電話のない生活
このブログを読んで下さっているお若い方々は、想像もできないかもしれませんが、私が幼い頃、私の自宅には電話がありませんでした。
念のために言っておきますが、携帯電話がなかったとか、スマホがなかったとか言うお話ではありませんよ。
家に固定電話がなかったのです。(今は固定電話がない家はたくさんあると思いますが、今とは違う事情で固定電話がなかったわけです。)
では、どうしていたかと言うと、父や母にどうしても用事がある人は、我が家のお隣さんが電話を設置しておられたので、お隣さんに電話をかけて、父や母を呼び出してもらうというシステムだったのです。
初めての黒電話
私が5歳ぐらいの時に、とうとう我が家にも電話なるものが、やってきました。
その日のことは、鮮明に覚えております。 人間、印象深い出来事や光景って、結構鮮明に覚えているものなんですよね。 どうして、そんなに鮮明に覚えているかと考えると、おそらく母がものすごくウキウキしていたからだと思います。
『今日は、電電公社の人が来るからねっ』
なんだ?電電公社?
そう思われたあなたっ!!あなたは、とてもお若い方ということになります。 電電公社ってのは、「でんでんこうしゃ」と読みまして、今のNTTさんのことです。 昔は公社だったんですよね~
その日、母の言っていた通り、電電公社のおじさんがやってきました。 作業服を着たおじさんが、何やら線をあっちからこっちから引っ張って、ややこしそうなことをやって、黒々とした黒電話を設置しました。 もっちろん、ダイヤル式ですよ。
電電公社のおじさんが、母に何やら説明をいっぱいして帰って行った後、私はあまりの珍しさに、黒電話の前に体育座りして、じっと電話を見つめておりました。
触れてはいけない番号
黒電話のダイヤルの真ん中に、なにやら数字が書いてある。
「110」「119」
『何だこれっ??』
そう思いながら、じっと体育座りして電話を見つめる5歳時・・・
危険を察知した母は、5歳児であった私に言いました。
『この番号に電話したら、怖いおじさんが飛んでくるんだからねっ!!』 『いい?絶対にここに書いてある番号に電話しちゃダメよ!!』
…はい、ここで問題発生です。
好奇心旺盛な5歳児に対して、絶対に言ってはいけない言葉を、母は口にしてしまったのです。
『絶対に~しちゃダメよ!』
これは、好奇心旺盛な5歳児に対して『どうぞ~しなさいよ』と言っているようなものです。
禁止されるほどやりたくなる心理(心理学的視点)
この現象は、心理学では「カリギュラ効果(カリギュラの禁止効果)」として知られています。
「してはいけない」と言われるほど、逆にやりたくなってしまう心理のことです。これは、禁止されることで「それが特別なものだ」と認識され、興味が増すために起こります。
特に子供は好奇心が強く、大人の言葉をそのままの意味で受け取るため、「絶対にダメ!」と言われると、「何がそんなにダメなの?」と興味を持ってしまうのです。
例えば、大人でも「この先立ち入り禁止」と書かれている場所に、妙に入りたくなることがあるのではないでしょうか?
この心理を理解しておけば、子供に注意するときの言葉選びが重要だということがわかります。「やってはいけない」と言うよりも、「〇〇するとこうなるよ」と、理由を伝える方が効果的なのです。
みなさんもあるでしょ? 『絶対に見ないで!!』なんて言っている人の引き出しに興味を持ったこと・・・
人間は、ダメと言われれば言われるほど、興味を持ってしまうのです。 まして5歳児。 好奇心の塊りです。
母がご近所に出かけたすきに・・・
ジーーーーーコロコロコロ(ダイヤルを回す音)
受話器からは『はいっ!!*●△×?です!!』と元気な声だけが聞こえました。
5歳児には何を言っているかは、聞き取れなかったのですが、 受話器から声が聞こえた途端、とっても怖くなって、電話をガシャンッ!!と切ってしまいました。
バレた!?消防署からの電話
何事もなかったように、ふふふーーーーーんっ♪としていたのですが、 母がご近所から帰ってきたときに、電話が鳴りました。
初の電話に喜び勇んで電話に出る母
受話器を持ったまま、何度も何度も頭を下げ、『すみません。すみません』と謝っています。
『やばい???』
危険を察知した5歳児は、脱走を試みましたが、母にとっつかまり、ひどく怒られました。
どうやら私が電話したのは、「119」で、先ほど母が電話で謝っていたのは、消防署の人に対してだったようです。
どうして我が家から電話をかけたことが、バレたのでしょうか? どうして、我が家の番号がわかったのでしょうか? ナンバーディスプレイなんて存在していない時代のはずなのに・・・
わからん・・・未だにわからん・・・
いたずらの代償と学び(心理学的視点)
この経験を通じて学んだのは、ただ単に「いたずら電話はダメ」ということではありません。
心理学では、「学習の経験効果」が重要だとされています。
実際に経験することで、自分の行動がどんな結果を生むのかを学び、それが記憶に深く刻まれます。今回のように、いたずら電話をして叱られた経験があれば、「次はやめよう」と学ぶのです。
また、「行動の結果が明確であると、学習は強化される」という心理学的な法則もあります。
このとき、単に怒るだけでなく、「なぜいけなかったのか」を説明することで、子供はただ怖がるのではなく、「これは迷惑をかける行為なんだ」と理解し、より深い学びへとつながるのです。
とにもかくにも、私が好奇心からダイヤルしてしまったことで、 消防署からおしかりの電話があり、私は母におしかりを受けるということになったのでした。
今の私がこの当時にタイムマシンでいけるなら、母に言ってあげたいですね。
『絶対に~しちゃダメ!は、絶対に言っちゃダメ!』
きっと母は、また『~しちゃダメ』と言うことでしょう。
まとめ
幼少期の経験は、私たちの行動や心理に大きな影響を与えます。
禁止されると逆にやりたくなる「カリギュラ効果」は、大人も子供も共通して持つ心理です。 また、実際に経験したことで学ぶ「学習の経験効果」は、子供が自らの行動の意味を理解し成長するために重要な要素です。
このように、「してはいけない」と言うだけでなく、その理由を伝えたり、行動の結果をわかりやすく示すことで、より良い学びにつながります。
※「私が子供だった頃」シリーズとして、過去の記事に加筆修正を行い、新しい内容を追加しました。