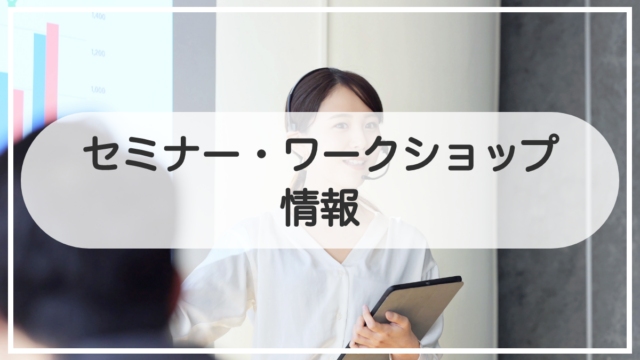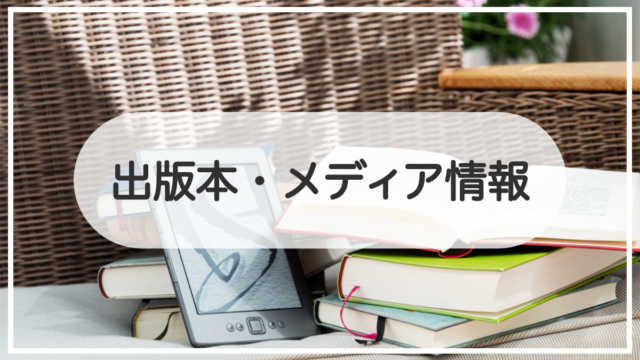職場で上司から「ちょっといい?」と声をかけられる。
その瞬間、心臓はドラムロール、頭の中ではホラー映画の予告編が上映スタート。
……実際の用件は「会議室のイス、並べ替えといて」だったりするのに。
なぜ私たちは、曖昧な一言にここまで振り回されてしまうのでしょうか?
そこには「曖昧さを嫌う心のクセ」と「自己肯定感」が深く関わっているんです。
「ちょっといい?」の破壊力
この万能フレーズ、使う人に悪気はありません。
でも聞かされた側、人によっては破壊力が桁違い。
- 自己肯定感が下がっているとき
「やばい、何かやらかした?降格?いや、クビ?」と心の中で人事異動会議が始まる。 - 自己肯定感があるとき
「昇進?ボーナス?それとも“社長賞”?」と勝手に表彰スピーチを考え始める。
同じ「ちょっといい?」なのに、ラブコメにもホラーにも化ける。
曖昧さに弱いのはなぜ?
心理学的に、人は「わからない状態」に耐えるのが苦手です。
これは 曖昧さ不耐性 と呼ばれる現象で、「結論が出ていない状態=不安」と感じやすい心のクセのこと。
たとえば…
- 上司から「あとで話そう」とだけ言われた日 → 会議までの数時間、仕事が手につかない。
- 気になる相手からLINEが既読スルー状態 → 「嫌われた?」「スマホ壊れた?」「事故?」と脳内でドラマ化。
- 健康診断の再検査通知 → 「余命◯年?」と一気にサスペンス映画。
本当はまだ何も起きていないのに、頭の中では空白を勝手にストーリーで埋めてしまう。
そして、その埋め方を決めているのは、自分の心の状態です。
- 不安が強いとき → 「悪いことに違いない」と破局的に解釈
- 自信があるとき → 「いい知らせかも」とポジティブに解釈
曖昧さはただの「真っ白なキャンバス」。
そこにホラー漫画を描くのか、ラブコメを描くのかは、自分の心次第なんです。
恋愛でも曖昧さはホラーにもラブコメにもなる
恋愛シーンでも、この「曖昧さの魔力」は健在です。
- ラブラブ期に恋人から「ちょっといい?」と言われたら
「え、プロポーズ?旅行のサプライズ?プレゼント?」と、頭の中でラブコメ映画がクランクイン。 - 関係がぎこちない時期に「ちょっといい?」と来たら
「別れ話?浮気発覚?ついに修羅場?」と、ホラー映画のBGMが流れ出す。
同じフレーズでも、心の状態によって解釈は真逆。
ここにも、自己肯定感の影響が色濃く出ています。
自己肯定感が左右する“解釈フィルター”
そもそも、自己肯定感は「どんな私でも価値がある」「どんな私も愛される」という感覚です。
そして本来、私たちは生まれたときには自己肯定感のかたまり。
赤ちゃんが「どうせ私なんて…」なんて落ち込んでいたら怖いですよね(笑)。
泣けば誰かが来てくれる。笑えばみんなが喜んでくれる。
そこには「私は存在するだけで素晴らしい」という揺るぎない自己肯定感があるんです。
けれど成長するにつれて、こんな経験が重なっていきます。
- 誰かと比べられて「それに比べてあなたは…」と言われる
- 失敗して笑われる
- 怒られて「存在ごと否定された」と感じる
こうした体験で心が傷つき、少しずつ「私ってダメかもしれない」と思い込むようになる。
つまり自己肯定感は“生まれつき低い”のではなく、“成長の過程で削られていく”のです。
自己肯定感が低いとき
曖昧さに直面すると、「私はダメな存在だから、悪い結果に違いない」と結びつけやすくなります。
- 上司から「ちょっといい?」 → 「あ、やらかした。降格かも」
- 恋人から「話があるんだ」 → 「別れ話に決まってる」
- 友達から「ちょっとお願いが…」 → 「きっと面倒ごとを押しつけられる」
自己肯定感が低いと、曖昧さ=「悪いことの前触れ」と自動変換されてしまうんです。
自己肯定感があるとき
一方で、「私は私でいい」と思えると、曖昧さを深刻に受け止めすぎません。
- 上司から「ちょっといい?」 → 「コピー取り?それとも昇進?まあ、どっちでも大丈夫」
- 恋人から「話があるんだ」 → 「サプライズ?仮に別れ話でも、私は大丈夫」
- 友達から「ちょっとお願いが…」 → 「協力できることかな?できる範囲で助ければいい」
自己肯定感はまさに 解釈フィルター。
ネガティブなフィルターをかければ曖昧さはホラーに見えるし、ポジティブなフィルターがあればラブコメに変わるのです。
自己肯定感を育てる工夫
では、どうやって自己肯定感を底上げしていけるのでしょう?
大げさなことをする必要はなく、小さな積み重ねで十分です。
- 「過去に“何も起きなかった”経験」を思い出す
(会議室に呼ばれたけど、実際はコピー取りだった…など) - 「まだ呼ばれただけ」と実況する
(“ドアが開いた”くらいの事実を心のアナウンサーで伝える) - 小さな成功や褒め言葉をちゃんと“自分の功績”にカウントする
(「ありがとう」を“ただの社交辞令”にせず、“自分が役立った証拠”として受け取る。メールの誤字を直せた、資料を時間内に作れた、そんな小さなことも“今日の成果”に加える)
こうした習慣が、「どんな私も大丈夫」という感覚を少しずつ取り戻してくれるのです。
まとめ
「ちょっといい?」にドキッとするのは、曖昧さそのものが怖いのではなく、自己肯定感の状態がどうかによって変わります。
本来、誰もが赤ちゃんのように「どんな私も愛される」と信じられる存在。
でも成長の過程でその感覚を失い、曖昧さをホラーとして描きやすくなってしまう。
自己肯定感を少しずつ回復させていけば、曖昧さをホラーにせず、ラブコメや日常ドラマとして受け止められるようになるはずです。
そして何より、心臓に優しい。
▼あわせて読みたい関連記事
未読ゼロにこだわる心理──通知の赤丸が気になって仕方ない理由
他人に振り回されない人は何が違う?自己肯定感を高める考え方と実践法
▼関連note記事
今回の記事は、noteで連載中のエッセイシリーズ
『“私だけ?”って思ってたけど、みんなそうだった。』#15「ちょっといい?に心臓がもたない」ともつながっています。
日常をユーモアたっぷりに切り取ったnote版も、ぜひあわせてお読みください。