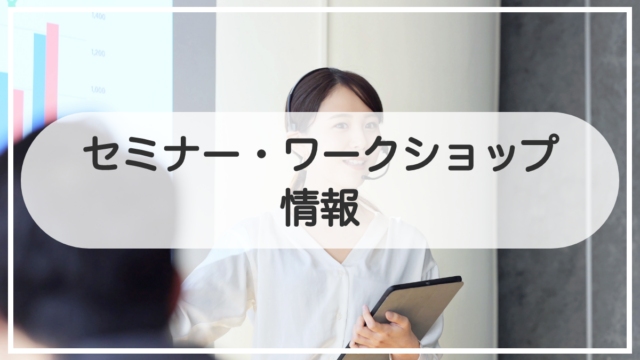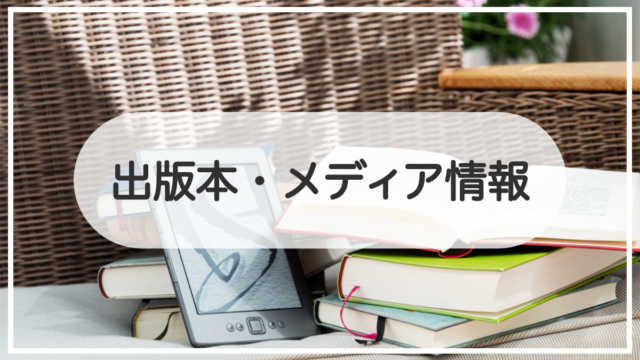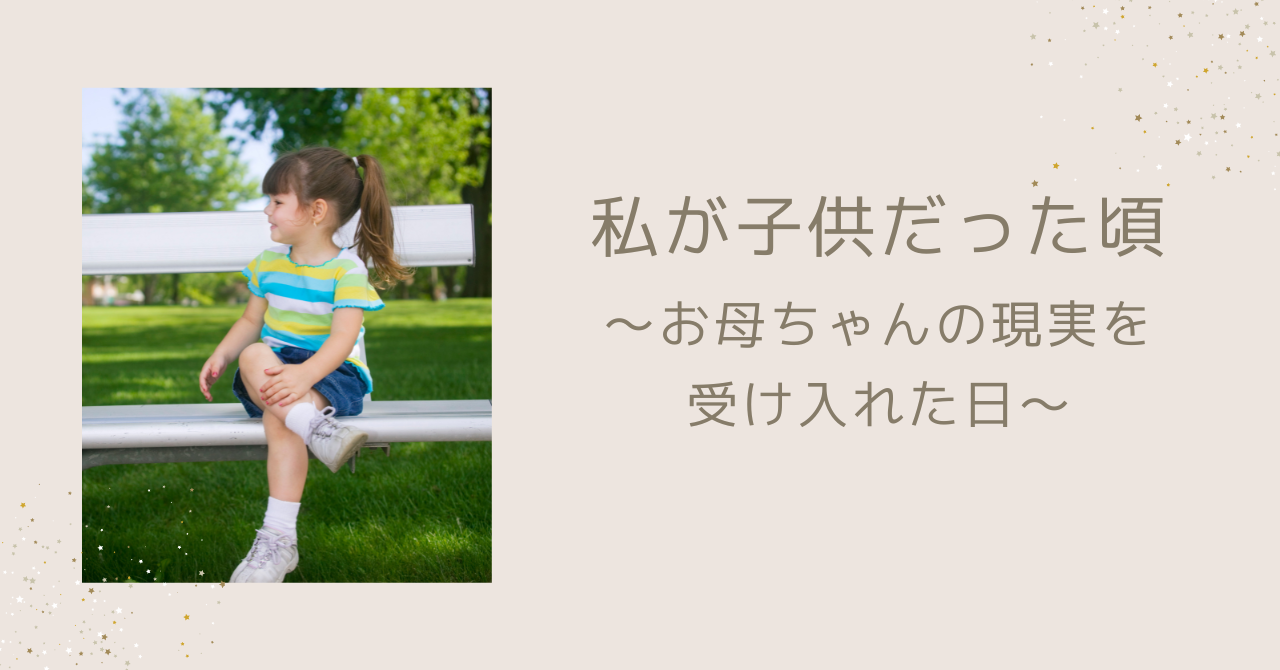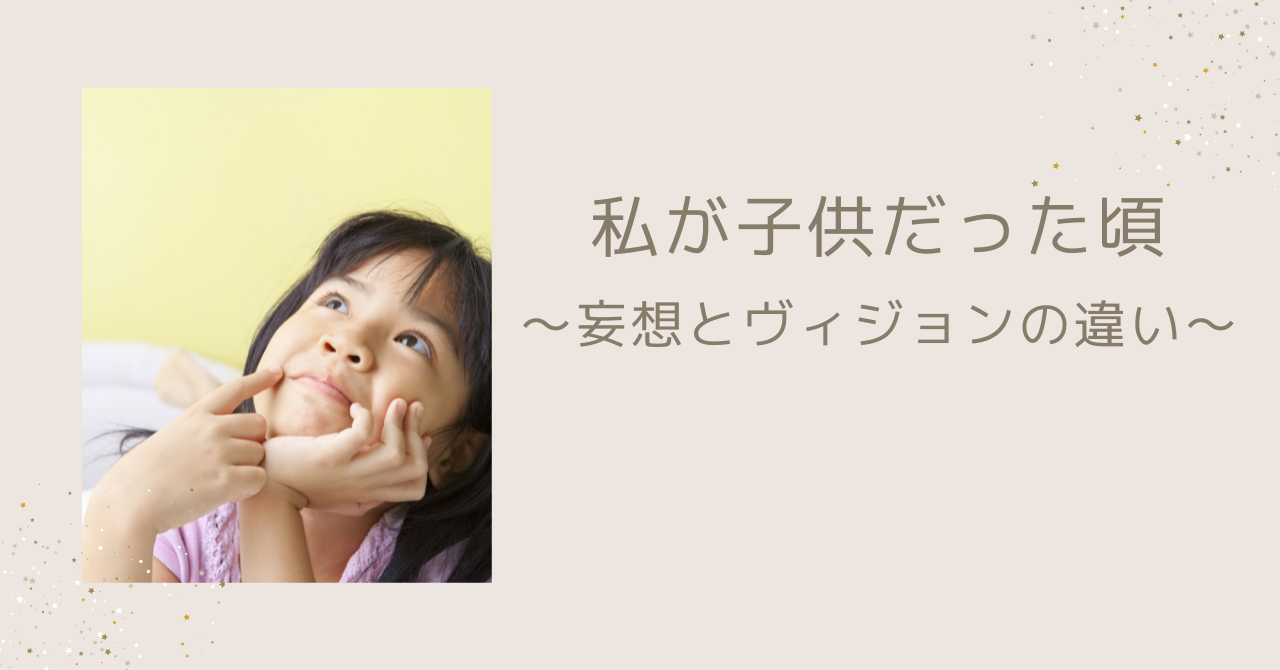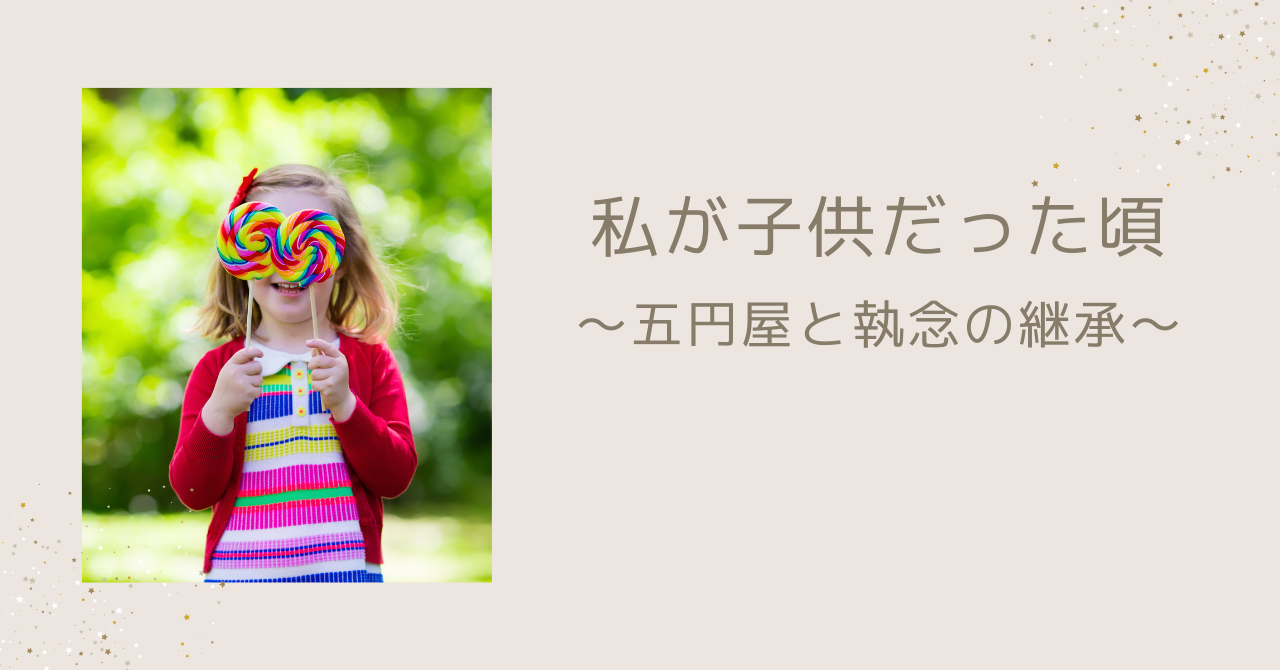お母様が迎えに来るはずだったのに
前回をお読みでない方は、こちら↓をご覧下さい。
妄想族であった私。 母が、お母ちゃんではなく、お母様であればいいのに・・・と日々妄想する。
そんなある日、近所の人達と一緒に、植物園に出かけたことがあります。 母は、私と兄を連れて、他の人は、それぞれ同じような年頃の子どもたちを連れて・・・
どんな駄々をこねたのか忘れましたが、どうやら私が駄々をこねたことが原因で、ひどく母に怒られたようです。 おそらく、近所の人がいるので、私の気が大きくなっていたのでしょう。 普段なら怖くて言えないことを、言ったのかもしれないですね。
怒られた私は、即座に妄想の世界に逃げ込みました。
『あの鬼の形相で怒っているお母ちゃんは、本当のお母ちゃんじゃないんだ』 『私の本当のお母ちゃんは、お母様で、もうすぐ私を迎えに来てくれる』 『お母様は、白い手袋をして、つばの大きな帽子をかぶり、綺麗なワンピースを着た、とっても美しい人なのだ』
そんな妄想をしつつ、近くにあったベンチに一人で座り込む。 母や兄、近所の人達は、そんな私に気付かず、どんどん進んで行く。
『ふっふっふっ・・・みんな行ってしまっていいのよ。もうすぐ本当のお母様が迎えに来てくれるんだから♪』
ところが、迎えに来たのは、当たり前と言うか、必然と言うか、鬼の形相をしたお母ちゃんであった。
『あんたっ!!何やってんの!心配したやないの!』
一気に現実に引き戻される幼児・・・
当たり前である。 私の母は、お母ちゃんなのであるからして、子供が一人姿を消したら、必死で探して迎えにくるのである。
この頃から、ある意味諦めたと言うか、受け入れたと言うか、『残念ながら、親を代えることはできない』と思ったのである。
攻撃性の抑圧と表面上の「良い子」(心理学的視点)
よって、身を守る為に、駄々をこねることはなくなった。 兄は相変わらず、母親にしょっちゅう逆らっていたので、よくお尻ペンペンされていたが、私は、みなさんのご想像に反して、とっても良い子になったのであります。 とは言っても、良い子なのは、表面上だけで、心の中では、よく悪態をついていたのである。
抑圧と攻撃性の現れ
心理学では、こうした攻撃性を抑え込むことを「抑圧」と言います。
抑圧された感情や欲求は、意識には上らないものの、態度や行動、さらには身体症状として現れることがあります。
例えば、「本当は怒りたいのに怒れない」という状況が続くと、怒りが無意識のうちに別の形で現れることがあります。
私のケースでは、母に直接反抗できない代わりに、心の中で悪態をついたり、態度や雰囲気が攻撃的になってしまったのだと考えられます。
また、心理学者アドラーによると、子供が「親に逆らっても意味がない」と学習すると、「過剰適応」の傾向を持つことがあります。 表面上は親の期待に沿って従順な子供になるものの、内面では不満やストレスを溜め込み、別の場面で爆発したり、心のバランスを崩すことがあります。
まとめ
この出来事を通して、私は「親を変えることはできない」という現実を受け入れるようになりました。
ただし、その受け入れ方は、単なる「納得」ではなく、「抑圧」を伴ったものでした。
心理学では、感情を抑圧することで、表面上は落ち着いているように見えても、その抑え込まれた感情が無意識のうちに表情や態度に現れることがあるとされています。
私が「怖い雰囲気」をまとうようになったのも、こうした感情の抑圧の結果なのかもしれません。
また、抑圧された感情は、後の対人関係にも影響を与える可能性があります。
例えば、子供の頃に「親に逆らえない」と感じた人は、大人になっても権威的な存在に対して過剰に従順になったり、逆に無意識のうちに敵対的な態度を取ることがあると言われています。
本当の意味で受け入れるとは、ただ我慢することではなく、抑圧せずに自分の感情を認めることなのかもしれません。
※「私が子供だった頃」シリーズとして、過去の記事に加筆修正を行い、新しい内容を追加しました。